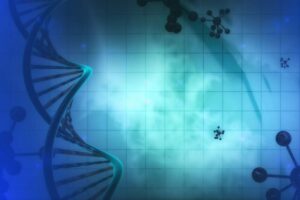「気になる事があれば話してみませんか?」小さな心配も、安心につながる一歩です。無理な勧誘などは一切ございませんので、がん治療でお困りの方はお電話またはLINEでお気軽に当院にお問合せ下さいませ。
四足のお肉(牛肉、豚肉)はがんリスクを上げる?
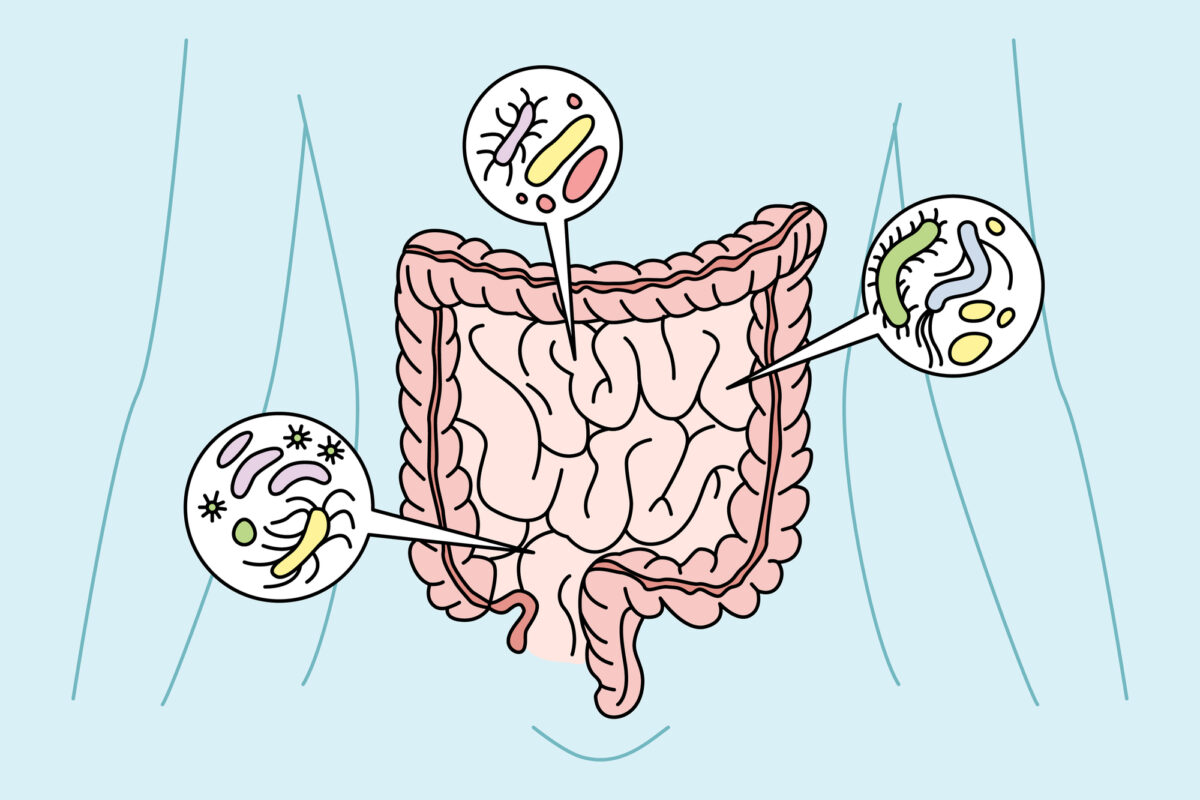
がんは異常細胞の増殖によって生じる病気で、体内の異常な細胞が無制限に増殖し、周囲の健康な組織に侵入することが特徴です。
がんは多くの要因によって引き起こされますが、食事習慣もその一因とされています。
どんな食べ物であれば食べ過ぎれば身体に毒ですが、豚肉や牛肉といった赤身肉(or加工肉)はがんリスクを上げるとWHOの研究機関である国際がん研究機関(IARC)から公表されています。
「この食品は身体に悪い」というエビデンスがあるものは少ない中で、なぜ私たちの生活に身近である赤身肉が良くないのか解説していきたいと思います。
豚肉や牛肉が「がんリスク」を上げる主な理由
- 動物性脂肪(飽和脂肪酸)
- 代謝の負担
- 塩分量(加工肉の場合)
- ヘム鉄(諸説あり)
動物性脂肪(飽和脂肪酸)
豚肉や一部の牛肉は比較的高脂肪であり、特に飽和脂肪酸の摂取が過剰であると、がんのリスクが増加する可能性があります。
どういう事か簡単に説明すると
①四足の動物のお肉は血液中にLDLコレステロールを増やします。
②LDLコレステロールは酸化すると免疫細胞のマクロファージが処理にまわる
③LDLコレステロールが増えすぎるとマクロファージがそちらの対応にいそがしくなる
④がん細胞が増えやすくなります。
ということです。
飽和脂肪酸は体内で炎症を引き起こし、がんの発症リスクを高めると考えられています。特に大腸がんや乳がんなどがんの一部のタイプに関連が見られます
代謝の負担
たんぱく質は肝臓でアミノ酸に分解されます。しかし、赤身肉の動物性たんぱく質は分解されにくく、身体に負担がかかりやすいといわれています。
塩分量
豚肉や牛肉から作られるプロセス肉(ベーコン、ソーセージ、ハムなど)には保存性や風味を向上させるために添加される塩、ニトライト、亜硝酸塩などの化学物質が含まれています。
塩分の取りすぎは胃の粘膜が荒れる原因となり、がんの原因であるピロリ菌などが増殖する一因になります。

実は日本人は海外に比べて塩分摂取量が多いので気を付けましょう。
塩分の過剰摂取は細胞の代謝異常がおきやすく、すべてのがんリスクが高まるといわれています。
ヘム鉄(諸説あり)
肉の一部にはヘム鉄が豊富に含まれており、過剰なヘム鉄の摂取が大腸がんのリスクを増加させると考えられています。
ヘム鉄は鉄分の一種で、腸内で特定の化学反応を引き起こし、がんの発症リスクを増加させる可能性があるといわれています。
しかし、国立がん研究センターの多目的コホート研究によると全体としてヘム鉄摂取と大腸がんの関連は見られないという結果もあります。
欧米ではヘム鉄と大腸がんの関連性について報告がありますが、ヘム鉄自体ががんリスクをあげるかどうかの結論はまだでていません。
赤身肉や加工肉を一切食べるな、ということではない
加工肉を毎日継続して1日あたり50g接種するごとに大腸がんのリスクが18%増加する、という公式の見解ではありますが、一切の摂取を禁じることを推奨しているわけではありません。
たとえば赤身肉には生き物が生きていく上で必要な栄養素(ビタミン、ミネラル)が豊富であり、妊娠前や妊娠中などの栄養補給として非常に優れています。
農林水産省は多くの種類の食品をバランスよくとることを推奨しております。



IARCの発表はあくまで加工肉の摂取を減らすことで大腸がんの発がんリスクを減らせるということを示したものです。
毎日食べるなら鶏肉とお魚をメインに
魚に含まれるオメガ3脂肪酸は心臓病予防にも効果があり非常に人体の身体に有用です。
鶏肉(白身肉)もがんリスクをあげる有害性は証明されていません。
毎日の食卓で動物性たんぱく質を摂取したいのであれば魚か鶏肉を候補にしてみてください。
まとめ
がんは体質や遺伝的な要素もありますが、1996年にハーバード大学が発表した研究によるとがんの原因の3割は食事によるものとされています。
がん細胞が好む食品を避け食べる量を減らせば、がんの発生リスクを抑えられるのでぜひ日頃から意識してみてください。